地区別焼酎の特徴
熊本と言えば球磨焼酎でしょう
球磨焼酎の産地である人吉市は、日本最古の焼酎の記録が
発見された鹿児島県大口市と隣合わせに位置し、
米どころとしても有名な場所です。
歴史上からみても、原料からみても、本格米焼酎の産地としては
確固たる地位を確立しています
粕取焼酎から変革する福岡の焼酎
福岡は清酒づくりを盛んに行っていた為、酒粕がたくさんできました。
その酒粕を蒸留してできた焼酎、いわゆる粕取焼酎では、全国でも
有数の産地だったのが福岡です。しかし、最近では生産量が極端に
減少し、代わりに麦焼酎を中心として全んどの種類の焼酎があるよ
うな状況になっています。その中でも特に、ゴマ焼酎は福岡の特産物
ともいえる焼酎です。
長崎県は清酒圏です。但し・・・
その中で壱岐だけはむぎ焼酎の島と言われるほど焼酎造りの歴史が深く、
現在、長崎全体の焼酎生産高の90%弱を造り出しています。
人口わずか40,000人の小さな島で造り出す量としては非常に多く、
米、むぎ焼酎の定着振りを伺うことができます。
大分県と言えばむぎ焼酎!
そんな大分ですが焼酎の歴史としては比較的浅く25年程前までは清酒
の方が定着していました。
大分県は焼酎ブームと一村一品運動により、今や歴史の深い壱岐地方
とも肩を並べるほどの、むぎ焼酎王国を築きあげたのです。
宮崎県は地域によって
違う焼酎が楽しまれています鹿児島に近い南部はいも焼酎、中央部は
いも焼酎と米焼酎、熊本に近い西部は米焼酎、大分に近い北部はソバ、
むぎ、トウモロコシ、粟などの雑穀焼酎と地域で飲まれる焼酎が違う
という特徴があります。ただ、鹿児島に次ぐいも焼酎の産地であり、
一般的にはいも焼酎の印象が強いようです。
芋焼酎の鹿児島県
鹿児島は芋焼酎のメッカである事は既に周知の事実でしょう。
から芋が育ちやすい温暖な環境のもと焼酎造りを始めた焼酎発祥の地で
あり、歴史的にも消費量から見ても間違いなく日本一の焼酎王国です。
「薩摩焼酎」は、世界ブランドへ。
「薩摩焼酎」は、ボルドー、コニャック、スコッチなどと同じく、
WTO世界貿易機関の協定に基づく産地指定を受けました。
【薩摩焼酎の定義及び薩摩マークについて】
鹿児島県産の良質なさつまいも、水を使い、鹿児島で製造から容器詰め
までのすべての工程を鹿児島県内で行った本格焼酎だけが、地域ブランド
としての「薩摩」を名乗ることができます。
2005年12月、「薩摩焼酎」は、ワインのボルドー、ブランデーのコニャック、
ウィスキーのスコッチなどと同じく、WTO(世界貿易機関)のTRIPS
(トリプス)協定に基づき「地理的(原産地)表示」として認められました。
「薩摩焼酎」は世界ブランドとしてさらに多くの人々に愛される焼酎へと進化
し続けています.
沖縄と言えば、言わずとしれた泡盛です
泡盛とは黒麹菌を使用して発酵させたもろみを蒸留したもので、沖縄で
造られるものだけを泡盛と呼ぶことができます。その歴史は中国から
15世紀に伝えられたということですから、本土の焼酎よりも歴史が古い
ことになります
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この続きは次回(本格焼酎の保存方法)ついて。。
飲酒は20歳になってから。未成年の飲酒は法律で禁止されています。
飲酒運転も法律で禁止されています
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
ほどよく、楽しく、いいお酒を。飲んだ後の容器はリサイクルにご協力ください。

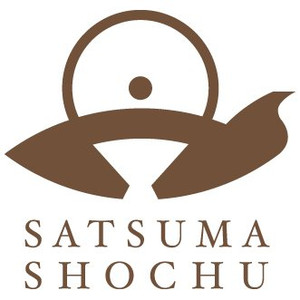


コメント