日本酒の行程
日本酒ができるまでには様々な工程があります。
精米(せいまい)
玄米の外側には蛋白質や脂肪など良い酒を造るのにじゃまなものが多く
含まれています。
それを取り除くために米を削ります。精米し終わった米は白米と言います。
洗米(せんまい)
白米に付いている糠を洗い落とす作業です。洗っている間にも米が水分を
吸収するので注意が必要です。
浸漬(しんせき)
白米に水分を吸収させます。浸漬の時間は米の品種や精米歩合によって変
ってきます。精米歩合の高いものは時間を計りながら洗米と浸漬を同時に
行います。
蒸米(じょうまい)
水切りをした後白米を蒸して糖化しやすくします。
製麹(せいぎょく)
麹室で麹菌を蒸し米に振り掛けて麹米を作ります。麹はデンプンをブドウ糖
に分解します。
酒母(しゅぼ)
麹と蒸し米と水をまぜ酵母菌を添加して、もろみを発酵させるのに必要な酵母
を培養します。
仕込み(しこみ)
酒母に蒸米・麹・水を3回に分けて増量していきます。これを三段仕込みと
いいます。三段仕込みをすることで酒母の酸やアルコールや酵母の密度を薄
めすぎないようにします。
タンクの中では麹がデンプンを糖に変え、酵母が糖をアルコールに変えてい
きます。これを並行複発酵といいます。
三倍増造酒・本醸造酒などは上槽直前のもろみに醸造用アルコールの添加を
行います。
上槽(じょうそう)
熟成したもろみを圧搾機にかけて搾ります。もろみは酒と酒かすに分かれます。
滓びき(おりびき)
搾った酒の濁りを沈殿させて抜き取ります。
ろ過(ろか)
タンクに活性炭を入れて酒の雑味や色を吸収させろ過機にかけます。
火入れ(ひいれ)[加熱殺菌]
酵素の働きを止めるために65度くらいに加熱します。
生酒は火入れをしません。
貯蔵熟成(ちょぞうじゅくせい)
熟成期間は酒質や用途によって異なってきます。
1月から1年位が普通ですが中には数年も貯蔵してある古酒もあります。
清酒も部 終わり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この続きは次回に(焼酎)について
ちょっと飲んでみるかい?
こいじゃが!!
ふざけんな!
なめてんか!
よくろぼ!が
ばかやろ!
”しょちゅのんごろ”の飲み会での会話みたいなラベル名
ちょっと呑んでみるかい
2000ml 麦 25度
こいじゃが
1800ml 芋 25度
ふざけんな
2000ml 焼酎甲類 25度パック
なめてんか
2000ml 焼酎甲類 25度パック
よくろぼ
1800ml 焼酎乙類 芋25度
ばかやろ
1800ml 焼酎乙類 米25度
飲酒は20歳になってから。未成年の飲酒は法律で禁止されています。
飲酒運転も法律で禁止されています
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
ほどよく、楽しく、いいお酒を。飲んだ後の容器はリサイクルにご協力ください。

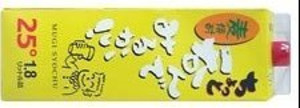
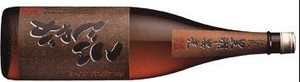

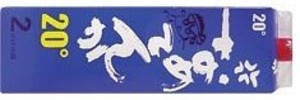
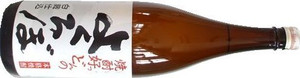
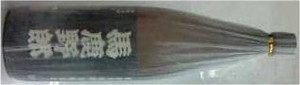

コメント